今回で8回目を迎えるフェスティバル/トーキョー、通称「F/T15(エフティー・ジュウゴ)」の記者会見とトークイベントに伺いました。
これまでのF/T記者発表エントリー⇒1、2、3、4、5、6、(7回目は出席できず)
複数人のディレクターが舵を取るディレクターズコミッティという体制になって、2度目のフェスティバル/トーキョーです。主催プログラムは12演目・3企画、連携プログラムは13演目、規模は例年同様に約3億円とのこと。アジア舞台芸術祭も同時開催されます。
記者会見では登壇されたアーティストの作品について紹介がありました。他の作品については公式サイトでご確認ください。8月末に詳細が公開されます。
【写真↓左より敬称略:市村作知雄、安野太郎、渡邊未帆、アンジェリカ・リデル、宮城聰、多田淳之介、山岸清之進】

●フェスティバル/トーキョー(F/T15) ⇒公式サイト
期間:2015年10月31日(土)~12月6日(日)の37日間
会場:東京芸術劇場、あうるすぽっと、にしすがも創造舎、アサヒ・アートスクエア、彩の国さいたま芸術劇場、池袋西口公園、豊島区旧第十中学校、ほか。
チケット一般発売開始:9月27日(日)10:00~
※先行割引チケット発売期間:9月23日(水・祝)10:00~9月26日(土)19:00まで
一般チケットの30%オフ!(『犀』は対象外)
―進行を務めます、ディレクターズコミッティ副代表の小島寛大です。まずはディレクターズコミッティ代表の市村作知雄より今年のコンセプト等についてご説明いたします。
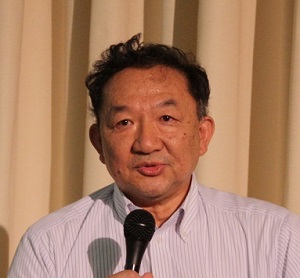
市村:去年、ディレクターズコミッティを立ち上げました。去年は立ち上げたところだったので、ほとんどの演目は私が決めていたんですけれど、今年はディレクターズコミッティという形が機能し始めて、複数のディレクターのもとでやる状態にほぼ近づいております。何年か継続してきてディレクター制の長所も欠点もわかりました。そこで考えをまとめ、次のステップへ行くための段階にしたいと思っています。その意味も含めてのディレクターズコミッティ、すなわちディレクター複数制です。
今年のテーマは「融解する境界」。去年が「境界線上で遊ぶ」でしたから、境界シリーズで継続性を保っていますが、今年は何を最も変えたかというと、デザインの部分を大幅に変えました。フェスティバル/トーキョーでは重くて強い課題のものを、軽く、明るくやりたい。今ここにいらっしゃる氏家啓雄さんにディレクターとして今年から参加していただいて、さまざまで、カラフルで、不思議な模様を使う形にしました。
コンセプトにはいくつかの大きなものがあります。「融解する境界」とは色んな境界線が消えていき、アートとアートじゃないものの境界線も消えていくということ。プレスリリースには「アーティストと言おうと、アクティビストと言おうと、社会を見つめ、地域を掘り下げることから世界に広がる創造的なことを展開する」と書きました。アートの境界すら消えていくだろうという意味です。一方で、去年、ヨーロッパの主要なプライム・ミニスターが一斉に「多様性は失敗に終わった」と記者会見をしました。当然その多様性を意識していまして、多様性を考えることが大きなテーマになっています。「多様性は失敗だった」と言いますが、そう簡単に失敗させるな、と言いたい。ただ同時に、欠陥があるのも事実です。多様性が対立をどうやって解決できるのか、その方法が見えない。多様性の中に対立をいかに含ませるのか。そういう厳しい作品が出来ていけばいいと思っています。
今年も主要な視線として、アジアにものすごく焦点を当てています。去年は韓国、今年はミャンマー、そして来年はマレーシア、再来年は中国と、既に進めて調整に入っております。去年はまだ「アジアについてやりたい」というぐらいにしか深まってなかったんですけど、さすがにもっと深めないとまずいと思いまして。アジアについて語る時、自分の立場を国家や社会の代表みたいなものに移し替えることが、人間には、できていきます。でも、アートにかんしてはそれをやるな、自分の立場を移し替えないで語れ、と言いたい。それに最も対応してくれるのが、岡田利規さんによる日韓共同製作の『God Bless Baseball』だと思うんですね。おそらく、自分を国という立場に移し替えないで、アーティストという立場にいることをちゃんと守って語ることは、アジアについて語る場合、非常に難しいことなんです。日本人がどういう立場でアジアを語るのか。アジアと一緒に創作することで問われることになると思います。やはりアジアの中で日本は非常に特殊な経緯を持っている国であり、その特性において、自分の立場を何らかの形に移し替えていくことが、常に起きるんです。アートがプロパガンダにならないための唯一の方法が、自分の立場を移し替えないことではないかと僕は思っています。
境界シリーズなので、ほとんどの部分は去年から引き継いでいます。去年のテーマはかなり長い射程を持っていると思っているので、すぐに変わるわけではなく、ちょっとずつ変えていこうと思っております。もうひとつの重要なテーマは東北の大震災と福島の原発事故です。今年も大きなテーマにしております。東日本大震災に対する僕の考えは、「震災をどう語るか」というところからアプローチしていません。「震災をどうとらえるのか」ではなくて、「震災を経験した中から生まれたもの」を取り上げたい。震災は非常に厳しい状況です。そういう厳しい状況に置かれると、人間は自分の限界を超えていくしかない。自分の限界を超えていく体験をしたところから生まれる作品は、相当すごいと思っています。昨年のプログラムでは『もしイタ』。『プロジェクトFUKUSHIMA!』も同じだと考えています。『プロジェクトFUKUSHIMA!』がなぜ素晴らしいのか。「ああ、あの方法を思いついたのか!」「あの方法を思いつけたのは、震災のおかげでしょう」と思っています。今年はもう1つ、飴屋法水さんが作った『ブルーシート』もやります。これも「震災をどうとらえるか」ではなくて、「震災を経験することで人間が変わったんだ」というところから生まれたものです。

こんなことを言うのはなんなんですけれど、先日、日本の首相が東北を訪問して仮設住宅の老人たちと会って、「(ご老人の)笑顔が忘れられない」とひとこと言ったということに、僕はさすがにショックを受けたんです。「仮設住宅の老人の笑顔が忘れられない」って、ちょっと、どうなのか。僕は「4年半も経ってなぜまだ仮設住宅があるんだ!(怒り)」と、かなり強い印象を受けました。そうと考えると、やはりそこから生まれたものについて、語り継いでいかなければいけないのかな、と。この方向性でもとらえていくべきかなと少し考えが変わりまして、それは来年以降にあらわれてくると思います。
アジアのもの、震災のものが中心になって組まれていますが、ヨーロッパのものについては作品本位で選んでいます。作品のインパクト、良し悪し、素晴らしさで選んでいるということです。もちろんフェスティバル・プログラムは「いい作品」という1つの価値で選べるものではありません。違った選び方があるからフェスティバルが成立している。いいものだけをやるのでは成立しないんです。1つひとつのテーマを考えながら、良し悪し以外の別のラインもあるということを示していこうと思います。
主催は12作品ですが、シンポジウムやサプライズ(隠し玉)を準備中です。東ヨーロッパのポーランドのものをやりたいと思っています。ポーランドといえば日本ではカントールがよく紹介されていますが、どちらかというとグロトフスキーを特集して組んでいきたい。アジアと同時に東ヨーロッパのものを、今年から始めて続けていきたいと思っています。東ヨーロッパは社会主義圏が壊れて、簡単に言うと、西側に負けていくわけですけれど、勝った方からよりも、負けていった方から、それを受け止めていく方から、いい作品が出てくる。そろそろ東ヨーロッパでいい作品が生まれてきているので、紹介していけたらと思っています。
短い時間ですので残念ながら全作品のご紹介はできません。先ほど申しましたようにディレクターズコミッティは機能し始めました。1つひとつの作品についての説明がしっかりプレスリリースに書かれているので、ぜひお読みいただければと思います。
最後にひとつ。我々がプロデュースする『ゾンビオペラ「死の舞踏」』については、始めからフェスティバルが一緒になって立ち上げていってます。一番わけのわからないもので、どういう作品になるのか全くわかりません。これが一番楽しみであり、怖いものでもあります(笑)。

―「プロジェクトFUKUSHIMA!」は2011年、東日本大震災をきっかけにスタートしたプロジェクトで、全国に大きな広がりを見せております。山岸清之進さんは今年から代表に就任されました。5年目となる今年のご活動、2年続けてフェスティバル/トーキョーに参加することについて、ひとことお願いできればと思います。
山岸:「プロジェクトFUKUSHIMA!」は大友良英さん、遠藤ミチロウさん、和合亮一さんという3人の代表によって、震災後すぐに立ち上がったプロジェクトです。私自身も福島出身で、活動当初から立ち上げに関わっておりました。最初は野外音楽フェスとして始まり、3年目に福島で盆踊りをしたところから、盆踊りが私たちの活動の中心になっていきました。日本の福島以外の場所からも声をかけていただくようになりまして、これまで愛知トリエンナーレや札幌国際芸術祭に呼んでいただいたり、多治見の小さな商店街の中でもやったりしました。去年のフェスティバル/トーキョーで池袋の西口公園でも盆踊りをやりました。5年目に入り、8月15日の『フェスティバルFUKUSHIMA!』でも盆踊りをやる予定で、今、準備を進めております。
活動の中心は8月15日に行う『フェスティバルFUKUSHIMA!』です。最初の年の野外音楽フェスは、放射能の汚染具合をどう判断していいのかわからないまま、専門家の指示に従って、線量計を持って、なんとか開催できる道はないかとやっていく中で、私たちが福島大風呂敷と呼んでいる大きなパッチワークの布が生まれました。あれがプロジェクトのヴィジュアル・アイコンのようなものになりました。会場に敷き詰めることで放射線量が軽減されるわけではないんですけれども、放射性物質が地面から靴の裏に付いたり、拡散したりしないので、被爆を避けられる。そういった意味で最初は作ったんですが、いつの間にか池袋、愛知、札幌にも敷かれるようになった。池袋と札幌は去年、今年と2年連続でやることになってまして、大風呂敷を、沢山のボランティア・スタッフもかかわりながら作っていくのが特に面白いです。先ほど多様性という言葉が出ましたけれども、そのプロセスでは多様な立場の人間が集まって、布も全国から集まるんです。池袋の場合はにしすがも創造舎が風呂敷工場になっています。福島だと大友さんのご実家が会場です。
その大風呂敷が今回も池袋に敷かれます。演奏は生演奏で、大友良英スペシャルビッグバンドや、盆踊りの伴奏をする盆バンドも登場する予定です。遠藤ミチロウも歌います。今年もまたこの熱狂を、お盆をはるかに過ぎた11月に体験していただけると思います。我々スタッフも一緒になって踊るのを楽しみにしているので、ぜひ記者の皆さんも一緒に踊っていただけたらと思っています。

―宮城聰さんには、シェイクスピアの戯曲を野田秀樹さんが潤色された『真夏の夜の夢』を上演していただきます。ラインナップ中、もっとも幅広いお客様に楽しんでいただける、そういう魅力を持った作品ではないかと思っています。静岡ではこの作品の上演中に中高生鑑賞事業も行われました。
宮城:『真夏の夜の夢』は静岡で2か月ぐらい、中高生を招待して見せていました。人間は100年ぐらいしか生きないから、大変なことが起こると「これは人類が初めて直面した危機じゃないか」とか「こんなことは歴史上誰も経験してないんじゃないか」とか、どうしても考えちゃうんですけれど、しかしそう考えたところで解決策を思いつくわけじゃないですよね。なのでやっぱり「似たような経験をかつて人類はしていないだろうか」と過去から学ぶこと。解決までいかないにしても、何とか持ちこたえる、こらえる知恵のようなものは、過去に似たような経験をした人たちから、学んでくるしかないのかなと僕は思っています。そのために芸術家になる側面があると思っているんです。
つまり芸術というのはこれまでの人類が危機に立ち向かった時、あるいは危機に耐え忍んだ時に生まれてきた、そういう知恵の集積じゃないかなと思っているんですね。ただ、色んな芸術の中で演劇は一番、歴史性というのを踏まえづらいというか、目の当たりにしづらい芸術です。たとえば書物や絵画であればかなり古いものを見ることができるけれど、演劇は生でしか観られないので、100年前の芝居を今観ようと思っても観られない。でも一方で、演劇ほど、その長い歴史を通じてバトンが受け渡されてきた芸術もない、とも言えるんですね。2500年前に書かれたギリシャ悲劇が今日なお、世界中の劇場で上演されてますから。
どういうことが起こってるかといえば、「本歌取り」とか「ないまぜ」とかいう手法が用いられながら、バトンが受け渡されていくんです。野田さんの『真夏の夜の夢』もまさにそういうものです。「本歌取り」と「ないまぜ」によって、シェイクスピアが今日の芝居に生まれ変わっている。日本の演劇で言えば能の『安宅(あたか)』が歌舞伎の『勧進帳』になってる。近松門左衛門が書いた『冥途の飛脚』は非常にシンプルだったのが、その後の『恋飛脚大和往来』になると、相当複雑な芝居になっている。そういうことが起こっていますね。全く同じことで、『真夏の夜の夢』の前半は舞台を日本に置き換えた形でスタートするんですが、後半ではなんとメフィストフェレスが登場します。まさに「ないまぜ」ですね。
やがてメフィストフェレスはパックのセリフを奪ってしまいます。メフィストフェレスは世界に対して恨みを持っている人間。世界に対して呪詛の言葉を一手に引き受けている存在として出てくるんだけど、僕が思うところ、これはまさに野田秀樹さん、あるいは劇作家そのもの。世界を恨む。でもなぜ恨むのか。それは自分を阻害した、自分を仲間に入れてくれなかった世界に対して、恨んでいる。だからメフィストフェレスこそが最も強く、世界とつながりたいと思っている存在なんですね。「劇作家ほど世界を恨みつつ、世界とつながりたいと思っている存在はいない」という話になっていくんです。こういう風に、現代の人間の孤独は、実は古代から続いているということが分かる。これが演劇のヒーリング効果なのではないか。孤独に直面している今の若い人たちに、演劇を観ることによって「こんなに昔からみんな同じことを悩んでたんだ」という風に感じてもらえれば。そして「僕は1人じゃないんだ。いや、僕は1人だけど、1人なのは僕1人じゃないんだ」と思ってもらう。そういう芝居だと考えています。

―『ゾンビオペラ「死の舞踏」』は、先ほど市村が、今回のフェスティバルトーキョーで唯一のプロデュース作品とご紹介いたしました、安野太郎さん、渡邊未帆さん、危口統之さんという3人の方々のコラボレーションです。安野さんの自動演奏楽器によるゾンビ音楽をフィーチャーしたオペラということで、まさに今、創作の真っ最中です。安野さん、渡邊さんから今考えていらっしゃること、どんな作品を生み出そうとされているのかを、お話しください。
安野:ゾンビと聞くと映画とかに出てくる、あの気持ち悪いゾンビを期待してしまうかもしれないですが、僕は僕自身の手で作ったロボットをゾンビと呼んでいて、それが演奏する音楽をゾンビ音楽と呼んでいます。『ゾンビオペラ「死の舞踏」』はゾンビ音楽によるオペラです。ゾンビやロボットによる表現というのは、昔から常に、人間や人間の社会を映し出す鏡として存在してきました。過去の巨匠たちが作ってきたゾンビものやロボットものがそうです。その点では、僕たちが発表しようとしている作品も例外ではないと思います。芸術そのものにも、我々や我々の社会を違う視点から見つめるという働きがあると思ってます。その1点において、『ゾンビオペラ「死の舞踏」』は、芸術や表現といわれるものの王道に忠実なものになると思います。今、渡邊さんと危口さんと3人で本当に話し合いながら進めていまして、ゾンビと呼ばれるロボットが奏でる奇怪な音楽が、人間や社会の一体何を映し出しているんだろうと、必死に耳を傾けて、それをどのように舞台に乗せていこうかと、試行錯誤の毎日です。

渡邊:安野さんからお話があったように、ゾンビオペラというのは、安野さんの自作楽器によるオペラです。オペラは西洋音楽史において何百年も連綿と続いてきて、発展してきた歴史があります。その中でどのようにオペラをとらえようかと考えた時、やはり時代、場所、状況による色々な条件づけの中で、その時の問題の解決をそれぞれに見出そうとする総合芸術が、オペラなのだと私は考えております。大きな主題としているのはテクノロジーと人間の関係性だと思います。機械を制御する人間と、人間による制御が不可能な機械、機械に制御されてしまう人間、そういったテクノロジーと人間の境界線。そのあたりについて3人で色々な意見を交わしています。『死の舞踏』というタイトルは、中世の時代に描かれて、いろいろ繰り返し語られてきた世界の崩壊の物語から来ています。今、ここに生きている私たちの表現として、このゾンビオペラがどのように描かれるか。そこに期待していただければと思います。
―多田淳之介さんは2013年にソン・ギウンさんと発表した『カルメギ 가모메』が、韓国で東亜演劇賞という非常に大きな賞を受賞されました。受賞が日本人初ということも大きな話題になりました。今回上演される『颱風奇譚 태풍기담』も多田さんとソン・ギウンさんが再びタッグを組む新作となります。多田さんはこれまでにも数々のシェイクスピア作品に取り組んでこられました。『テンペスト』を題材にした背景や、今回もまた日本と韓国との共同製作になりますので、今、どういう形で進んでいるのかをお聞かせください。

多田:ソン・ギウンさんとのご縁は古く、僕自身は2008年から韓国で活動を始めて、もう7年になります。ギウンさんの劇団と僕の劇団との共同製作は毎年行ってまして、2013年に韓国のドゥサン・アートセンターのプロデュースで作った『カルメギ 가모메』で賞をいただきました。今回の『颱風奇譚 태풍기담』は、僕が芸術監督をしている富士見市民文化会館キラリ☆ふじみという、埼玉県富士見市のとても小さな市の劇場と、韓国のソウル市内にある南山アートセンター、そして安山文化芸術の殿堂との3館で始めたプロデュース公演で、そこに東京都も入って上演されることになります。韓国の劇場と日本の地域の劇場で活動している僕個人としましては、劇場同士で作品を作ることは悲願でしたので、今回実現したことを嬉しく思っています。
南山アートセンターはソウルにありますが、安山文化芸術の殿堂がある安山市は、日本で言えば富士見市ぐらいの距離感覚です。ちょっと特別なのは、去年4月16日にセウォル号沈没事故があり、その船に乗っていた生徒たちの学校、ダンウォン高校がある市なんですね。そこでも僕は色々活動をしていまして、そういう特別な意味のある場所なので、個人的にも楽しみです。
『カルメギ 가모메』はチェーホフの『かもめ』をベースに翻案し、舞台を日帝朝鮮に置き換えました。『颱風奇譚 태풍기담』もシェイクスピアの『テンペスト』が題材で、『カルメギ 가모메』は1930年代だったんですが、今回は1920年代を背景にして作ります。『テンペスト』なので島の話になります。数日前に第一稿が上がってきたところなので、まだこれから色々変わると思いますが、日韓で島の話をすると、結構…やっかいなことも出てくるんですけど…。最初は『ロミオとジュリエット』をやるという案もあったんです。日韓でモンタギュー家とキャピュレット家という風に、わかりやすくやろうと。以前に僕がソウルで作った『ロミオとジュリエット』がけっこう評判が良かったので、またちょっと新しく作ろうかと。でも、『ロミオとジュリエット』はまずいという話になったんですね。なんでだろうと僕は思ったんですが、ギウンさんと話をしたら「ロミオとジュリエットの仲が悪い原因がわからない。なぜ仲が悪いのかが描かれていない。それは韓国ではちょっとまずいかもしれない」と。平等に仲が悪いとダメみたいです。
『カルメギ 가모메』もそうだったんですが、外国の古典戯曲を自分たちにどう引きつけるかに興味があります。シェイクスピアのお話をいかに私たちのお話にできるかがポイントだと思っています。そこを楽しみにしていただければと思います。

―最後はアンジェリカ・リデルさんです。現在東京で6日間のワークショップを実施していただいており、記者会見へのご出席も叶いました。『地上に広がる大空(ウェンディ・シンドローム)』は2013年のウィーン芸術週間のオープニング作品として上演され、非常に多くの反響を集めました。この舞台には「ピーターパン」の少女ウェンディーが登場し、2011年にノルウェーのウトヤ島で起きた銃乱射事件(69人の10代の若者が殺された)の後、彼女は上海へと飛び立って行きます。なぜ「ピーターパン」をモチーフに作品創作をすることにしたのか、また、日本での初招聘について、考えていらっしゃることをお話しください。
リデル:この作品では3つの島が舞台になります。ウトヤ島、ピーターパンのネバーランド、そして私にとって島である上海。また3つのテーマがあります。1つは青春の喪失、つまり若さがなくなってしまうこと。若者が殺されることとピーターパンが成長しないことも含まれます。もう1つが見捨てられたことの恐怖。そして母親に対する憎悪。この3つを扱います。
ウェンディーの復讐という形で筋が進みます。ウェンディーの復讐とは母親に対する憎悪も含め、実は私自身が持っている復讐です。私の憎悪をどういう風にしてウェンディーと同一化したらいいかと考え、アンネシュ・ブレイビクがウトヤ島で69人を殺害したことと、自分を同一化しようと思いました。ピーターパンは成長しません。そう考えると、ブレイビクが殺した69人の若者はピーターパンと同様に「これ以上成長しない」というシチュエーションになったわけです。逆に言えば、ブレイビクという人はピーターパンの夢を実現した人ということになります。
初めて上海に行って驚いたのは、路上や広場で上海の人たちが踊りまくっていたこと。すごくショックを受けたので、翌年、また上海に行ってその人たちに「私はあなた方と仕事がしたいので、ぜひともヨーロッパに来てください。ヨーロッパに来たからって人を食うようなことはありませんから、大丈夫です」と説得して、ヨーロッパに連れて行きました。さらに私の中にあった1つの夢は、韓国人のチョ・ヨン・ムクという作曲家に作曲をしてもらうこと。この芝居の中で踊るワルツの音楽をオリジナル楽曲にしたかったので、その人に作曲を依頼して引き受けていただきました。

記者:グリーンとピンクの新しいフェスティバルトーキョーのロゴについて、デザインをされた氏家啓雄さんに直接、その思いを伺いたいです。
氏家:僕は30年ぐらい前にアーティストだった時期があって、その後は「ウゴウゴルーガ」などのテレビの仕事をしていました。今回、市村さんに声を掛けられて、「ロゴを変えたい。明るいものにしたい」と言われました。
市村さんもよく知っているパリ在住のアーティストのnaomiを使ってみないかという話になり、彼女に何枚も描かせてるうちに1枚、すごくいいのが出てきたんです。天岩戸をイメージしていまして、FとTの硬いロゴが開いたところから、演劇や音楽の明るいイメージが湧き出してくるというのが僕の思いです。
≪トークイベント「2020年にむけて、アートフェスティバルの展望」≫
登壇者(敬称略・順不同):
市村作知雄(F/T15 ディレクターズ・コミッティ代表)
宮城聰(アジア舞台芸術祭ディレクター)
芹沢高志(さいたまトリエンナーレ2016ディレクター)
吉本光宏(ニッセイ基礎研究所研究理事/東京芸術文化評議会 評議員)
撮影・録音禁止でした。以下、私がメモした内容です。どなたの発言かは一部、伏せました。

・F/Tが始まったのは2009年だが、前身のフェスティバルは1988年からスタートしているので、もう約30年の歴史がある。世界最大級のフェスティバルはエディンバラとアヴィニョンで、両方とも1947年から70年弱の歴史がある。F/Tは30年だから、だいぶん近づいている。このまま継続して欲しい。
※アヴィニョンは演劇祭になったのが1947年から。前身となるフェスティバルは美術家が1943年に立ち上げていた。
・単純な規模拡大が成功ではない。
・アーティストは夢を見る天才。自分が生きる未来を夢見るトリエンナーレにする。それを導くのがアーティスト。
・まつりの後が気になる。東京オリンピックは2020年だが、それ以降のことも考えておかないと。長い目つきが必要。
・とりわけ東北、福島と関係を持ち続ける必要がある。
・アヴィニョンでフェスティバルが始まった1943年はというと、フランスはドイツに占領され、多様性が否定されていた。一色に染められたくない美術家たちがフェスティバルを立ち上げた。多様性をどう担保するか、という動機からフェスティバルが始まっている。
翻って、正反対の例もある。例えば1936年のナチス政権下のベルリンオリンピック。「民族の祭典、美の祭典」と謳う芸術競技があり、テーマはスポーツ、都市計画、建築などがあったが、金メダルを一番多く取ったのはドイツだった。1940年に日本でオリンピックが開催されていたら、きっと同じことをやっただろうことは想像に難くない。
ソチオリンピックの閉会式ではロシア人の芸術家にフィーチャーしていた。多様性の尊重とはむしろ正反対。国の結束を高める道具に使われた。うっかりすると、そういう使われ方もするのがオリンピック。2020年の東京オリンピックが多様性を担保するものであることを、心の底から願わずにはいられない。
・宮城:2500年前の作品が今も上演され続けているのが演劇。演劇の歴史性に気づいてほしい。学校で教えられている音楽や美術とは違って、演劇は歴史を知られていない。踏まえられていない。SPACのレギュラーシーズンでは、演劇の教科書に載るような演目で、演劇の歴史と地理がわかるような作品を上演している。レギュラーシーズンを2~3年続けて観れば、演劇の世界史を知ることが出来る。
・宮城:演劇を通じて、今日の悩みの解決の糸口となる、過去の知恵とアクセスできる。たとえば現代の若者が悩む孤独、孤立は、実は過去のたくさんの人に耐え忍ばれてきたものなのだ。
・宮城:SPACの年1回のフェスティバルでは、「これも演劇なの?!」というものを観てもらう。演劇の領域を拡張していく仕事を観てもらう。
・宮城:アジア舞台芸術祭はF/Tの10分の一の予算でやっている。今年で10年目。私にとってはSPACが9年なので、こちらの方が長い。コラボレーションの方法を考えるのがアジア舞台芸術祭。
・宮城:『アンティゴネ』を池の水を抜いて上演した。それを観てくれた韓国人の演出家にコラボレーションを持ちかけられ、一緒に『トロイヤの女』をやることに。「自国の歴史で『トロイヤの女』から何を想像する?」と聞いた。朝鮮戦争と答えるかと思いきや、「壬辰倭乱(じんしんわらん)」と返事された。自分は「原爆だ」と答えると、「たった1日、2日のことで被害者面しないで欲しい。こっちは一体何年、日本に占領されたと思っているんだ」と言われた。「激昂しないでこんな話が出来ている自分に驚いている」とも言われた。
・集客は大切。でもタレントは使いません。
≪フェスティバル/トーキョー15 (F/T15) ≫
会期:平成27(2015)年10月31日(土)- 12月6日(日)
会場:東京芸術劇場、あうるすぽっと、にしすがも創造舎、アサヒ・アートスクエア、彩の国さいたま芸術劇場、池袋西口公園、豊島区旧第十中学校、ほか
主催:フェスティバル/トーキョー実行委員会
豊島区/公益財団法人としま未来文化財団/NPO法人アートネットワーク・ジャパン、アーツカウンシル東京・東京芸術劇場(公益財団法人東京都歴史文化財団)
フェスティバル/トーキョー15:http://festival-tokyo.jp/
※クレジットはわかる範囲で載せています。順不同。正確な情報は公式サイト等でご確認ください。
~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~
★“しのぶの演劇レビュー”TOPページはこちらです。
便利な無料メルマガも発行しております。